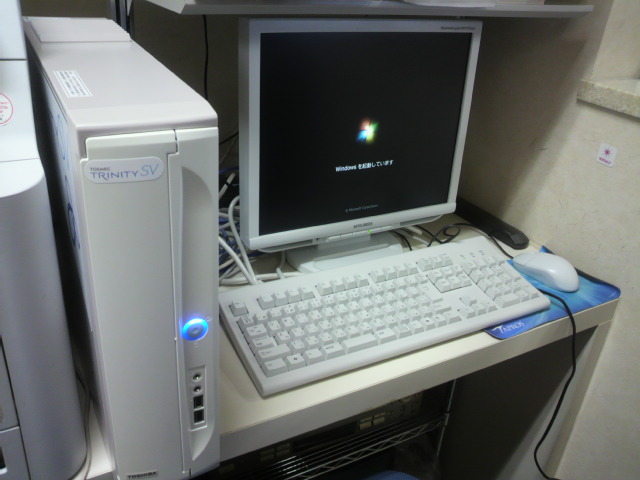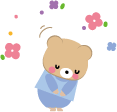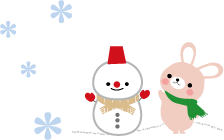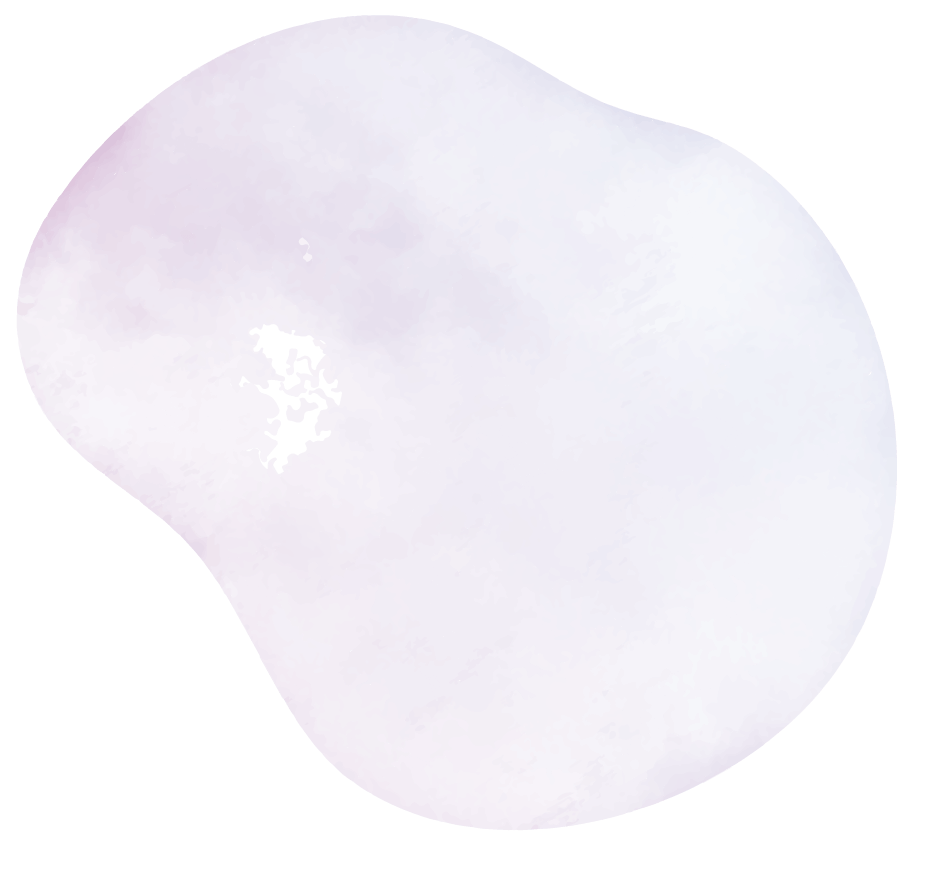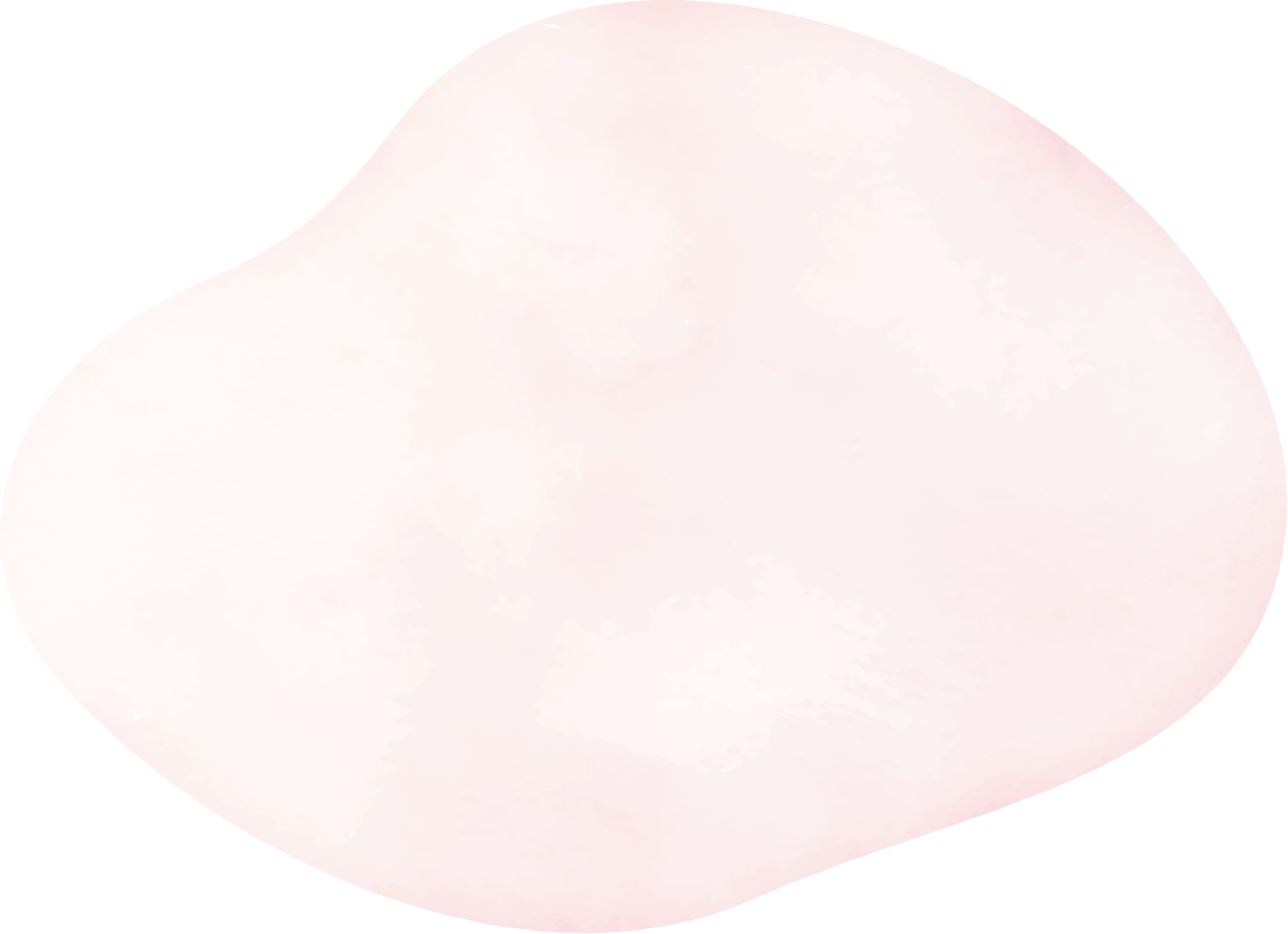感謝
2015.08.17
お暑い中、いかがお過ごしでしょうか。
さて、まるひさ眼科は8月1日をもちまして、14周年目を迎えました。これも、皆様の笑顔や優しさに支えられてきたお陰であると、院長はじめ、スタッフ共々感謝の気持ちでいっぱいです。今後とも、日々よりよい医療が提供できるよう努力いたしますので、何卒よろしくお願いします
2012.01.01
2011.12.17
2011.08.15
2011.08.01
お陰様で、2011年8月1日をもって当院は開院10周年を
迎える事になりました。
これも皆様のご指導とご愛顧があってのこと思います 。
心より感謝申し上げます 。


振り返ってみると、あっという間の10年間でしたが、
本当にさまざまな出来事がありました。
開院当初を思うと、 全てが一からのスタートであり、
暗中模索しながら医院を運営してきました。
皆様には大変御迷惑をおかけしたことと思います。

10年という月日の中で、医療も大きく変化し、
医療機器も随分進歩しました。
当院でも、光干渉断層計(OCT)、IOLマスター、
最新の白内障手術装置
「INFINITI OZil® IP搭載」を導入しました。
その他の機械についても、メンテナンスが欠かせなくなり、
時間の経過を感じます。
また、 外壁も塗り替え、看板もリニューアルしました。


患者様お一人おひとりを大切に…
信頼してくださる皆様の気持ちに応えれるよう、
院長、スタッフ一同
日々精進して参ります。


今後とも宜しくお願い致します。
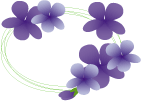
月別アーカイブ
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年7月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (3)
- 2019年10月 (2)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年1月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (1)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年3月 (3)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (1)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (1)
- 2014年11月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (2)
- 2013年11月 (1)
- 2013年10月 (1)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (2)
- 2013年6月 (1)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (1)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (1)
- 2013年1月 (2)
- 2012年12月 (1)
- 2012年11月 (2)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (1)
- 2012年8月 (1)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年5月 (1)
- 2012年4月 (1)
- 2012年3月 (1)
- 2012年2月 (1)
- 2012年1月 (3)
- 2011年12月 (1)
- 2011年10月 (2)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (2)
- 2011年6月 (2)
- 2011年5月 (1)
- 2011年4月 (2)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (1)
- 2011年1月 (3)
- 2010年12月 (2)
- 2010年11月 (4)
- 2010年10月 (2)
- 2010年9月 (4)
- 2010年8月 (3)
- 2010年7月 (3)
- 2010年6月 (4)
- 2010年5月 (3)
- 2010年4月 (3)
- 2010年3月 (3)
- 2010年2月 (3)
- 2010年1月 (4)
- 2009年12月 (3)
- 2009年11月 (5)
- 2009年10月 (4)
- 2009年9月 (4)
- 2009年8月 (6)
- 2009年7月 (6)
- 2009年6月 (5)
- 2009年5月 (8)
- 2009年4月 (2)